「もう限界かも…」そう感じながら、今日も仕事と家事、育児に追われていませんか?
共働き生活に疲れ果て、「退職しかないのでは?」と検索したあなたは、きっと毎日頑張りすぎている人です。
私自身、夫が単身赴任で親のサポートなしの完全ワンオペ。
フルタイムで働きながら、2人の子どもの育児と家事を回す日々に、限界を感じたこともあります。
だからこそ伝えたいのは、退職=唯一の選択肢ではないということ。
退職を決断する前に、あなたが本当に手放すべきことを一緒に整理してみませんか?

✅7歳&4歳の2児の母
✅フルタイム30代管理職×夫単身赴任で不在
✅“頑張りすぎないワーママの暮らし”をサポートする情報を発信中。
∟フルタイムママ歴6年・単身ワンオペ歴2年
∟メンタルヘルス・マネジメント検定(Ⅱ種) 取得
∟ポジティブ心理実践インストラクター資格 取得
✅当ブログのミッションは「苦労するワーママをひとりでも減らしたい!」です
「退職したい…」と思うのは、甘えじゃない

毎日、仕事をこなしながら、家事も育児も完璧にこなす——
そんなふうに、“がんばること”が当たり前になっていませんか?
でも、本当にそれ、当たり前にしていいのでしょうか?
実際、Domaniのアンケートによると、30〜45歳のワーママ100人のうち、約85%が「疲れた」「しんどい」と感じた経験があると回答しています。
つまり、疲れているのは“あなただけじゃない”ということ。
現代の共働き家庭において、無理を前提に回っている“仕組み”そのものに問題があるのです。
「限界」は“キャパ不足”ではなく、“構造の問題”かも
そう感じてしまうのは、あなたの能力が足りないからではなく、役割や負担のバランスが崩れている状態が長く続いているから。
たとえば──
- 夫婦で“共働き”なのに、家事・育児の負担が自分に偏っている
- 自分の時間が全然とれない
- 睡眠時間が削られ、いつも疲労が抜けない
- 頼る先がなく、抱え込んでいる
こうした状態が続けば、どんな人でも「もう仕事やめたい」と思って当然です。
「退職したい」と思うのは、あなたが弱いからじゃない
退職を考えるのは、甘えではなく心と体が出している“正当なサイン”です。
しかし、それは“退職するしかない”という意味ではありません。
まずは、「何をやめるべきか」を丁寧に見つめ直すことが、共働きの負担感から抜け出す一歩になります。
本当にやめたいのは“仕事”ですか? 退職しもっと苦しくなることも…

共働き生活が限界に感じると、ふと「いっそ辞めてしまいたい…」と思ってしまいますよね?
仕事を辞めれば、家事や育児に専念できて、時間や心にも少し余裕が生まれるかもしれない――
そう考えるのは、ごく自然なことです。
けれど現実は、そうはならなかった…という声も少なくありません。
むしろ、辞めたことで以下のような新たな負担や不満が増えてしまうケースすらあるのです。
①家事・育児の“全担当者”になってしまう
仕事を辞めた途端、家族から「家にいるんだからやって当然」という空気が漂い始めることがあります。
夫の家事・育児への関与がますます減ってしまい、結局、育児も家事も“フルで一人”に押しつけられる状態に。
そんな状況に追い込まれてしまうことも。
②お金の自由がなくなり、さらに孤独を感じる
仕事を辞めた後は、自由に使えるお金がグッと少なくなる可能性も高まります。
「ちょっとコンビニで買う」「たまにカフェに行く」そんな小さな楽しみすら、ためらうように。
家にいてもリフレッシュできず、むしろストレスが蓄積してしまうことも。
また、社会とのつながりがなくなることで、誰にも評価されず、誰とも会話しない日が続く孤独感に苦しむ人も意外と多いのです。
③退職後の再就職は、思っている以上にハードルが高い
「また余裕ができたら働けばいい」と思っていても、一度キャリアを手放すと、同じ条件・待遇で再就職するのはかなり難しいのが現実。
保育園や学童の利用にも制限が出てしまい、「働きたくても預け先がない」という悪循環に陥ることもあります。
疲れ切っているときほど、「いっそ仕事をやめてしまえばラクになるかも」と思ってしまうもの。
でも実は、生活全体の“仕組み”に目を向けることこそが、根本的なラクへの第一歩かもしれません。
「本当にやめたいのは、仕事なのか?」それとも「頑張りすぎる生活」「1人に偏った家事育児」なのか?
しっかり、見極めることが大切です。
退職の前に「やめていいこと」から始めてみよう

「もう限界。仕事を辞めるしかないのかな…」
そう思ったときこそ、いきなり大きな決断をする前に、“やめていいこと”を手放すことから始めてみませんか?
仕事を辞めれば、たしかに仕事の負担は減るかもしれません。
でも実際には、「辞めてもラクにならなかった」「むしろ家事と育児の負担が増えた」という声も少なくありません。
大切なのは、「本当に今、何をやめたらラクになるのか?」を見極めること。
ここでは、私自身が実際に試して効果を感じた“やめてよかったこと”を3つご紹介します。
1. 家事の“やめる”を決めた(料理編)
平日の夜、子どもを迎えに行って、疲れた体でごはんを一から作る。
そんな日々に心身ともに限界を感じていた私は、思い切って宅配食サービスを導入しました。
以前は「休日の作り置き」で乗り切ろうとしていましたが、結局そのせいで休日に負担が集中し、リフレッシュできないという本末転倒な状態に。
宅配食サービスに変えてからは──
そして何より、仕事終わりの「今日のご飯どうしよう…」というストレスから完全に解放され、毎日がぐっとラクになりました。

我が家では、つくりおき.jpというサービスを取り入れることで週に3-4日夕飯づくりを手放すことができています。
宅配食サービスは、今や40社以上あるとも言われています。
だからこそ、「どれを選べばいいのか分からない…」と迷ってしまう方も多いはず。
そこで、私が実際に使ってよかったと感じたサービスを、厳選して3つだけご紹介しています。
「うちにはどれが合ってるかな?」と悩んだときの参考に、ぜひチェックしてみてくださいね。
2. 家事の“やめる”を決めた(掃除編)
掃除も毎日やろうとすると、時間も気力も奪われます。
そこで導入したのが、ロボット掃除機と週1回の家事代行サービスです。
「全部自分でやらなきゃ」という思い込みを手放すだけで、“余白のある暮らし”に変わりました。

タスクを、家族以外にも分散したことで、どちらかが動けなくなっても家事が回るようになり、リスク回避にもつながりました。
「部屋が完璧であること」よりも、自分が笑顔でいられることの方がずっと大切だと実感しています。
3. 完璧を目指すのをやめた
部屋をきれいに保つ、子どもに優しく接する、仕事でもちゃんと結果を出す――
いつの間にか、“完璧な母であり、妻であり、社会人であること”を自分に課していました。
でも正直、それってすごくしんどい。
無理して頑張るほど、笑顔が減っていく自分に気づいたんです。
だから今は、「ま、いっか」って思える心の余白を大切にしています。
洗濯物をたたまない日があっても、部屋におもちゃが散らかっていても、「誰かが死ぬわけじゃないし、今日も一日ちゃんと生き抜いた。
「それだけで十分えらい!」って、自分に言ってあげられるようになりました。
小さな「やめる」が、心の余裕を生む
みなさんも、気づかないうちに「全部自分がやるのが当たり前」になっていませんか?
“やめる”と決めることで、初めて見えてくるものがあります。
まずは、料理・掃除・思考のどれか1つでもいい。
「やめても大丈夫なこと」から少しずつ手放していきましょう。
その一歩が、「退職」よりも先に心をラクにする確かな一歩になるかもしれません。
それでも退職したい時、どう備える?【現実的な選択肢】
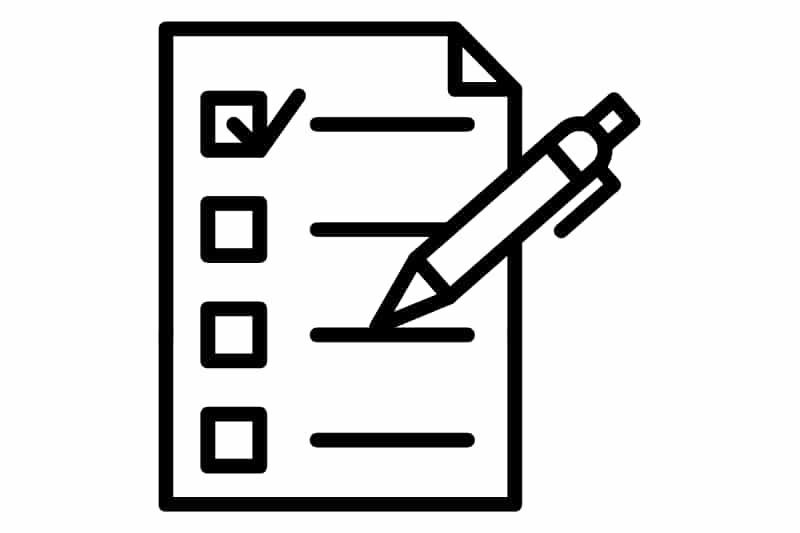
ここまで「やめてもいいこと」「手放してもいい思い込み」を見直してきました。
それでもなお、「やっぱり退職したい」「この働き方はもう続けられない」と感じることもあるでしょう。
そんなときに大切なのは、感情だけで決断せず、冷静に選択肢と準備を整えていくことです。
ここでは、退職以外も含めた“現実的な選択肢”と、実際に辞めるときにしておきたい準備について整理していきます。
1. 時短勤務の継続・延長という選択
正社員として働き続けたいけれど、今のフルタイム勤務はしんどい…。
そんなときは、まず「時短勤務」を会社に相談してみましょう。
育児時短勤務は原則「子どもが3歳まで」とされがちですが、企業によっては小学校入学まで延長可能な制度を設けている場合もあります。
時短=評価が下がると感じるかもしれませんが、体を壊してしまっては元も子もありません。
一度ペースを落とすことで、長く働き続けられる可能性も広がります。
2. 異動・休職という選択肢
実際、異動によって環境がガラッと変わり、負担が大幅に減ったケースもあります。
また、「心の病」を理由とした休職制度を整備している企業も増えているため、ひとりで抱え込まず相談してみることが大切です。
3. 退職を選ぶなら、事前の準備がカギ
どうしても退職を選ぶ場合は、「辞めてから考える」のではなく「辞める前に整えておく」ことが非常に大切です。
以下の3点は、事前に必ず確認・準備しておきましょう。
● 保育園・学童の継続条件を確認する
退職後も子どもを預けられるかどうかは、自治体によって異なります。
「求職中扱い」になる猶予期間(たとえば3ヶ月)や、就労証明書が必要なタイミングなどは、退職前にしっかり調べておくこと。
● 社会保険・扶養の切り替え
退職後は、健康保険や年金の切り替え手続きが必要になります。
夫の扶養に入る場合/任意継続する場合/国保に切り替える場合で、条件や手続きが異なるため注意が必要です。
● 家計の見直しと“片働き”試算
収入がなくなることを前提に、
- 毎月の固定費をどこまで削れるか
- 教育費や保険などの見直しポイント
- 貯蓄で何ヶ月耐えられるか
といったシミュレーションをしておくことで、退職後の不安を軽減できます。
退職という選択肢は、決して逃げではありません。
でも、「辞めたらラクになる」と思って飛び出してしまうと、かえって苦しくなることもあるのが現実です。
だからこそ、選択肢を広げながら、“辞める準備”をするところから始めてみてください。
それだけでも、心が少し軽くなり、冷静に自分の今と向き合えるようになるはずです。
まとめ|“やめること”から、あなたの生活は変わる
退職を考えるほど、毎日が苦しいと感じているみなさんに伝えたい。
毎日本当にお疲れ様です!!!
でも、「退職するか、しないか」だけが選択肢ではありません。
まずは、がんばりすぎている今の生活の中で、やめてもいいこと・手放してもいい思い込みをひとつずつ見つけていくこと。
それが、心と体をラクにする第一歩になるはずです。
退職は、“逃げ”でも“悪いこと”でもありません。
ただし、大切なのは「やむを得ず辞める」のではなく、「自分で選んで辞める」状態に整えていくこと。
そのためにも、生活や思考の中にある“やめていいこと”を少しずつ減らしていくことから始めてみましょう。
あなたと家族が、もっと笑顔で、もっと心に余裕を持って過ごせる方法は、必ずあります。
焦らず今のあなたに合ったペースで、ひとつずつ見直していってくださいね。
以上、こんママでした。

当ブログでは、
①ワーママが楽しく得やメリットをえるための「ワーママ術」
②「子どもの学び」にも楽しさを取り入れる重要性
について発信しています。
という方には、こちらの記事もおすすめです!
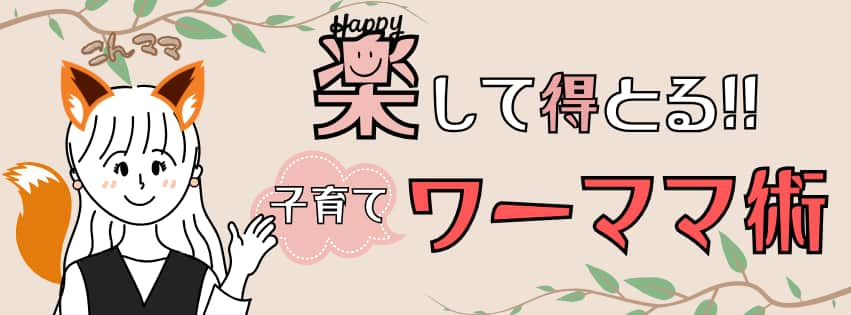
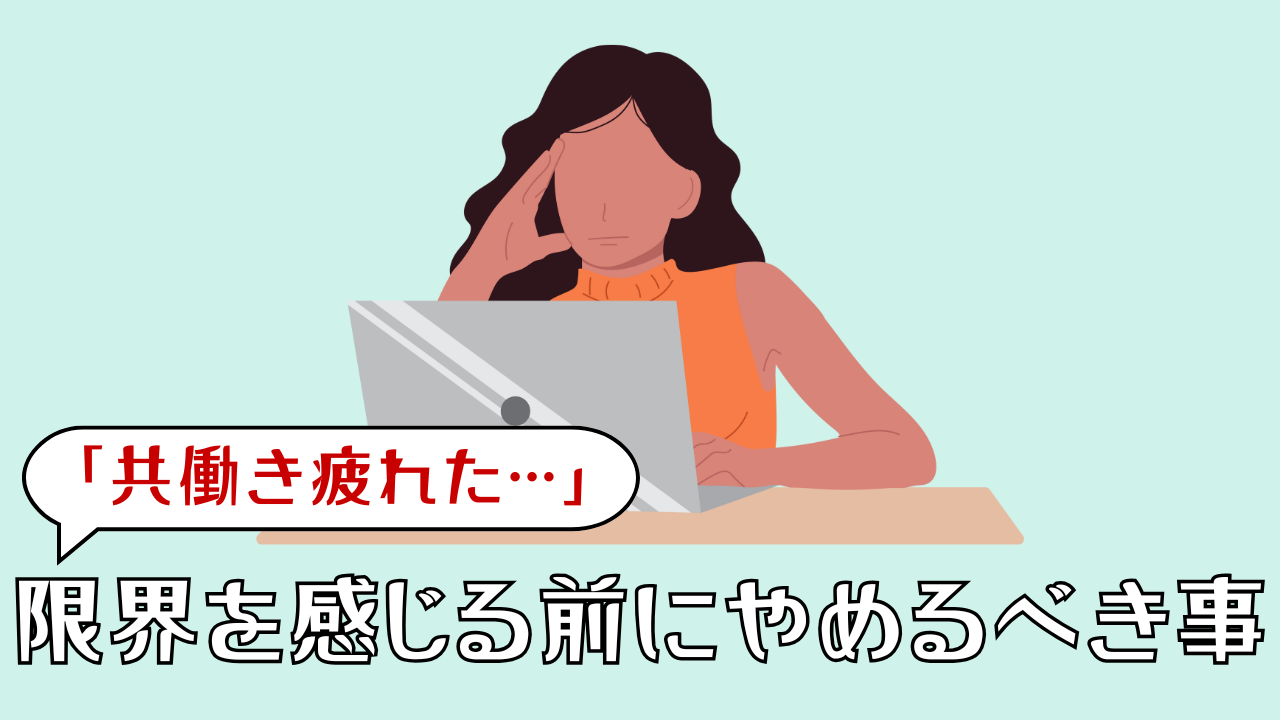






コメント