
共働き大変すぎる!

家事、育児、仕事に追われてしんどい
私自身、夫が単身赴任で不在、二人の子どもを育てながら働く日々に限界を感じていた時期がありました。
寝不足と焦りで心も体もボロボロになり、家族との時間すら楽しめなくなったこともあります。
そんな私が今元気で活気ある毎日を取り戻せたのは、「やめていいこと」を決め、「不要なタスク」を手放したからでした。
この記事では、子育てにおける時期別の大変さや、私自身が共働きの大変な時期を乗り越えるために手放した4つのことを紹介します。
共働きで毎日疲労困憊の方は、ぜひ最後まで読んでください。

✅7歳&4歳の2児の母
✅フルタイム30代管理職×夫単身赴任で不在
✅“頑張りすぎないワーママの暮らし”をサポートする情報を発信中。
∟フルタイムママ歴6年・単身ワンオペ歴2年
∟メンタルヘルス・マネジメント検定(Ⅱ種) 取得
∟ポジティブ心理実践インストラクター資格 取得
✅当ブログのミッションは「苦労するワーママをひとりでも減らしたい!」です
共働きが「大変」と感じる理由

共働きがつらいと感じる背景には、共通するいくつかの原因があります。

まずはその原因を整理して、自分がどこで一番負担を感じているのかを確認してみましょう。
ワンオペ化による負担増
夫婦で共働きのはずが、実際にはどちらか一方が家事や育児を抱え込んでしまうケースは少なくありません。
特に相手の帰宅が遅い場合や、我が家のように単身赴任な場合、実質的にワンオペ状態になり、心身ともに大きな負担がかかります。
タスク多重化(仕事・育児・家事が同時進行)
仕事と家事、さらに育児を同時進行でこなすことは想像以上に大変です。
朝は子どもの登園準備と自分の出勤準備、帰宅後は夕食づくりと宿題チェックなどなど分単位でタスクが迫っています。

時間に追われる生活が続くと、余裕がなくなりストレスが積み重なりますよね。
コミュニケーション不足からくる夫婦間トラブル
忙しさで夫婦の会話やコミュニケーションが減ると、「分担が不公平」「気持ちがわかってもらえない」という不満が募りやすくなります。
感謝の言葉が減り、指摘や不満ばかりが増えると、家庭内の雰囲気も悪化。さらにストレスが大きくなってしまいます。
こうした要因が重なっていくと、「大変すぎてもう無理!」と限界を迎えてしまうことも…。
子どもの時期別にみる子育ての大変さ
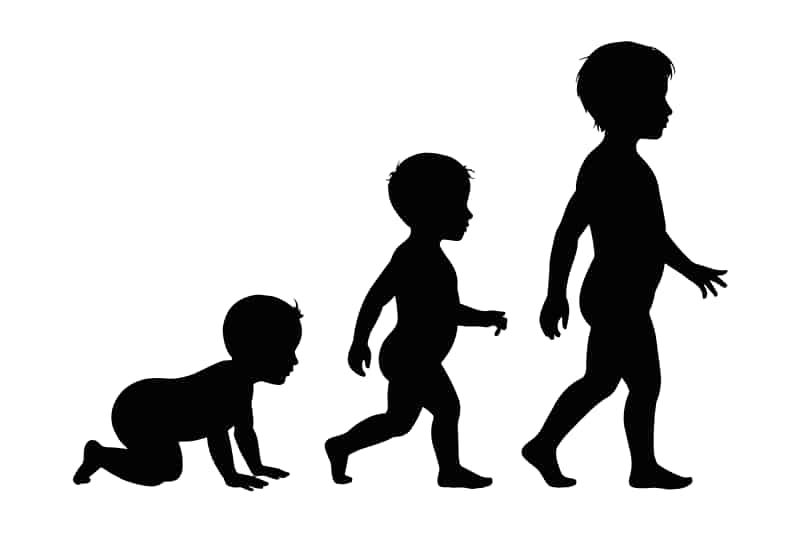
でも、安心してください。
子どもが成長するにつれて、共働き家庭が直面する悩みや負担は少しずつ形を変えていきます。
「今が一番つらい!」と思っていても、成長とともに状況は必ず変化します。まずはそれぞれの時期でどんな壁が立ちはだかるのかを整理してみましょう。
乳児期:夜泣き・授乳・体調不良で睡眠不足
この時期はとにかく寝不足が深刻です。
夜泣きや授乳で何度も起き、まとまった睡眠が取れないまま朝を迎える日々。さらに乳児は体調を崩しやすく、急な発熱による予定変更が頻発します。
親の体力とメンタルが大きく消耗する、もっとも負担が重い時期です。

私は一人目が生後3か月のころに産後鬱になりかけました。しんどかったー…
幼児期:イヤイヤ期・送迎ラッシュ・家事負担増
自我が芽生え、イヤイヤ期が始まると、登園準備や外出などことあるごとに大騒ぎ。
「着替えたくない」「行きたくない」という子どもを説得するだけで時間が過ぎてしまいます。
加えて、保育園だけではなく習い事を始める家庭が多い時期です。送迎回数が増えその分負担が増す時期です。

予定が常に子供の起源に左右され…精神的にも肉体的にも疲弊しやすい時期です。
小学生期:学童問題・宿題・長期休みの過ごし方
小学校に進学すると、子どもは新しい環境に適応するために親のサポートが欠かせません。
この時期は、宿題や家庭学習のフォローに加えて、学校行事や習い事の送迎など、親が関わる場面が一気に増えます。
また、保育園では延長保育を利用できることが多いですが、小学校の学童保育は終了時間が早く、利用時間に制限が出てくるケースもあります。

その結果、親は仕事を早めに切り上げる必要があり、時間的な制約がさらに増して、ワーママにとって大きな負担になりやすい時期です。
このように、実は、子どもが成長するにつれて悩みがゼロになるわけではなく、形を変えて新たな課題や大変さが必ず現れるのが真理です。
だからこそ、「無理して頑張りすぎない」ことが大切。
普段から少しでも余白をつくり、心身にゆとりを持てる仕組みを整えておくことが、長く続けていくための鍵になります。
精神的負担・限界を示すサイン
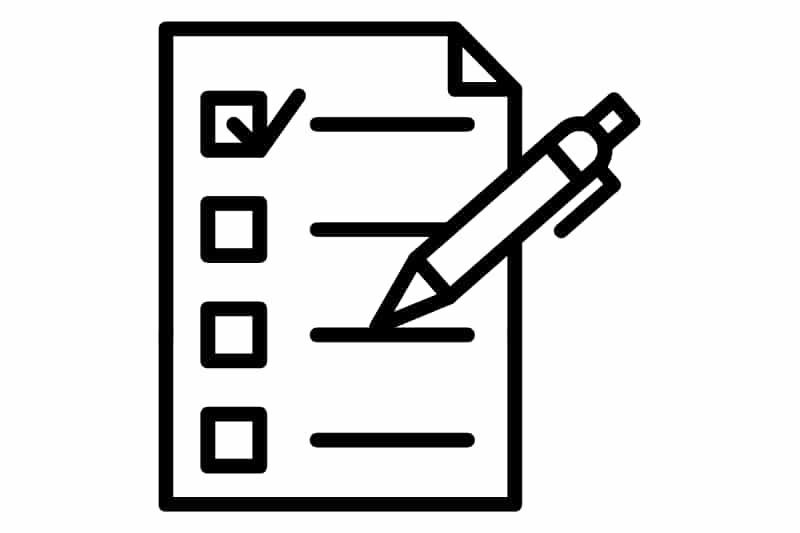
共働きで頑張り続けていると、自分では気づかないうちに心と体が悲鳴を上げていることがあります。
ここでは、無理をしているサインを客観的に確認できるチェックポイントを紹介します。一つでも当てはまるものがあれば、休息や負担軽減の方法を意識的に取り入れることが大切です。
身体的サイン
身体のSOSを放置し続けてしまうと気づいたときには、慢性的な不調や大きな病気につながることもあります。

私の周りでも体調をくずしてしまったワーママが多くいます。決して軽視しないようにしましょう!
精神的サイン
精神的な限界は、自分ではなかなか認められないもの。気づいたときには、かなり無理を重ねている状態です。
家族への影響
無理を続けていると、自分だけでなく家族にもストレスが広がります。
家族が安心して過ごせる空間を守るためにも、まずは自分の心と体を大切にすることが必要です。
複数当てはまる方は要注意です。
このまま無理を続けるか、それとも自分を守るために負担になっていることを手放すかが、分かれ道になります。

今すぐできることから少しずつ「やめる」選択をしていくことが、心と体を守る第一歩です。
【リスト付き】頑張りすぎママが“やめていい事”4選
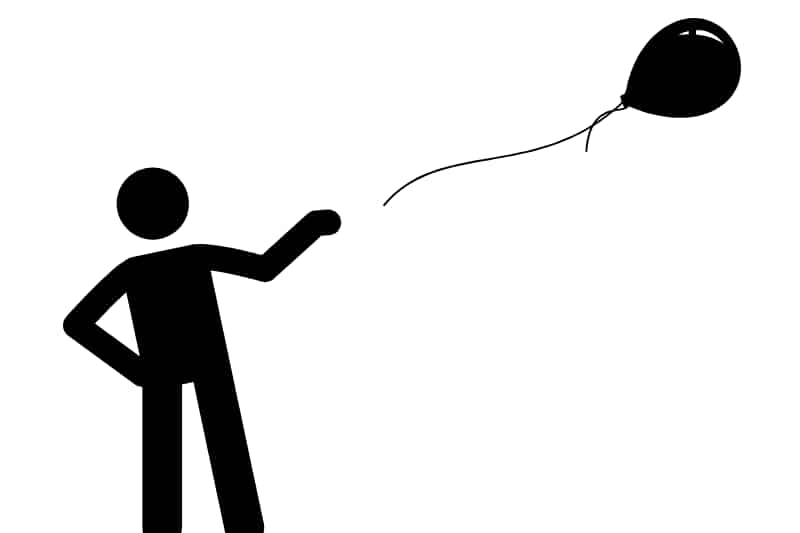
すべてを自分で抱え込む必要はありません。
「私がやらなきゃ」と思い続けていると、心も体も疲れ果ててしまいます。

私自身、夫が単身赴任で不在の中、二児をワンオペで育てながら、職場では新規事業の立ち上げを担当していました。
そんな日々の中で、子どもの体調不良が続いて何度も保育園から呼び出され、深夜までの仕事と看病で眠れない日もありました。。
「もう無理かもしれない」と思う瞬間も一度や二度ではありません。
それでもなんとか乗り越えてこれたのは、すべてを自分で抱え込むのをやめ、「やめていいこと」を少しずつ手放す努力をしてきたからです。
ここでは、私が実際に手放してきた4つのことをお伝えしていきます。
以下の4つを少しずつ手放すことで、あなた自身がラクになり、自分にも家族にも笑顔が戻ってきますよ。
①料理をやめる
毎日発生する家事は、ワーママにとって心身ともに大きな負担になりがちです。

私自身、いくつかの家事を見直してきましたが、その中でも料理時間を減らすことが一番効率的で、得られるメリットも多いと実感しています。
もともと料理が得意ではなく、「仕方ないからやっている」という感覚でしたが、外部サービスや便利な仕組みに頼ることで時間も心の余裕も生まれました。
その結果、子どもと過ごす時間が増え、自分自身も笑顔でいられるようになったんです。
もし今、料理をイヤイヤこなしているのであれば、それは見直す絶好のタイミングかもしれません。
ぜひ下記のブログを参考に、あなたに合ったスタイルを見つけてみてくださいね。
②掃除を手放す
「家を常にキレイに保たなきゃ」という思い込みは手放してOK。
ルンバなどのロボット掃除機や家事代行サービスを頼れば、毎日の掃除は最低限で十分です。
平日はサッと片づけるだけにして、週末は思い切って完全オフにするなど、自分の時間を優先しましょう。

我が家は、自分での掃除を手放しロボット掃除機と週1の外部サポートで回す仕組みにしてから2年立ちますが、このスタイルでも十分お家の清潔さは保てています。

③買い物をやめる
毎日の買い物に時間を使うのは大きな負担です。
宅配食サービスを使えば買い物の負担も減りますが、さらに、負担を軽くしたいのであれば普段からネットスーパーや定期宅配を活用して「買い物時間ゼロ」を目指しましょう。
冷凍ストックや常備食品を上手に組み合わせれば、買い物の回数を大幅に減らせます。
④残業を減らす工夫
仕事での残業が続くと、家庭との両立がますます難しくなります。
定時退社を優先する働き方を意識し、業務の優先順位を見直しましょう。
チームメンバーや上司に現状を共有し、無理なく回せる体制を整えることが大切です。

そんなこと言っても、職場の雰囲気的にむずかしい…

わかります。私もかつてそう思っていました。
ただ、ワーママという立場は本当に大変で、常に仕事と家庭の板挟みになります。
そして、無理をし続けた先に待っているのは、心身の不調や家族との関係悪化など、何ひとつ良いものではありません。
健康に代わるものはありません。
倒れてから後悔しても、時間も関係も取り戻すことはできないのです。
私自身も、かつては月40時間以上の残業を抱えていたワーママでした。
しかし、思い切って働き方を見直し、チームとの調整を繰り返した結果、持ち帰り仕事ゼロの働き方にシフトすることができました。
以下の記事では、私が実際に行った残業削減の具体的な工夫と対策を紹介しています。
同じように「仕事が終わらない…」と悩んでいる方は、ぜひこちらの記事もよんでみてください。
無理を減らす工夫は、自分と家族を守る大事な選択です。
まずは一つでも手放してみることで、暮らしがぐっとラクになりますよ。
まとめ|“やめる”選択で共働き生活をラクに
共働きは、家事・育児・仕事が同時進行で発生するため、誰にとっても負担が大きいものです。
さらに、子どもの成長に合わせて悩みの形も変わります。
乳児期は夜泣きや体調不良で寝不足になり、幼児期はイヤイヤ期や送迎ラッシュ、小学生期には学童の終了時間や宿題対応など、新たな課題が次々と押し寄せてきます。
しかし、この大変さは永遠に続くわけではありません。その時期特有の壁は「やめる」「手放す」ことで軽減することができます。
私自身、何度も「もう無理!」と思ったことがあります。それでもなんとか乗り越えてこれたのは、“やめる”勇気を持ち、不要なタスクを少しずつ手放していったからです。
完璧を目指さなくても大丈夫。
あなたがラクになることが、家族全員の笑顔につながります。まずは今日から、ひとつだけでも「やめる」選択をしてみてください。
以上、こんママでした。

当ブログでは、
①ワーママが楽しく得やメリットをえるための「ワーママ術」
②「子どもの学び」にも楽しさを取り入れる重要性
について発信しています。
という方には、こちらの記事もおすすめです!
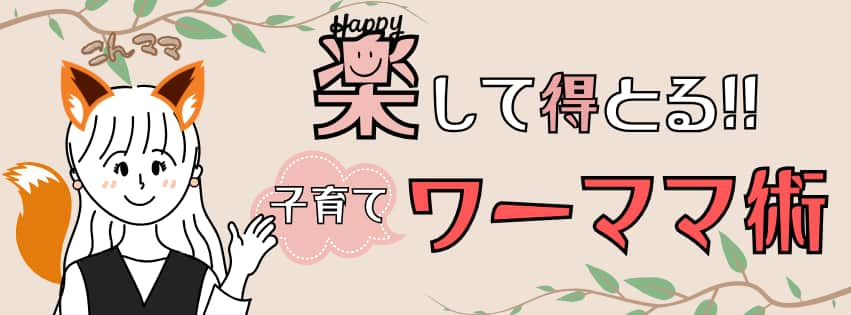







コメント