新小学1年生の4月、どんなスケジュールになるのか不安ですよね?
そんなママたちに伝えたいのは、「全部を完璧に把握しなくて大丈夫」ということです。
実際、4月は学校側もイレギュラー続きで、親も子も手探りで進んでいく期間です。
だからこそ、がんばって抱え込むより、“手放すこと”が大切なんです。

私自身、初めての「小1の壁」を、年少の娘を抱えながら、単身赴任中の夫もいない中で迎えました。
正直、不安もありましたが、「やらない選択」を意識したことで「小学校1年生の春」を無理なく乗り越えることができました。
この記事では、気になる4月のスケジュールや、振り回されないための心得と準備を3つにしぼってご紹介します。
親子で迎える「小学校1年生の4月」を、少しでも安心して過ごすためのヒントとして、ぜひ参考にしてくださいね。

✅二児の母(7歳&3歳)
✅フルタイム管理職×夫単身赴任で不在
✅ワーママが「楽しく」生きるためのヒントを発信中
∟メンタルヘルス・マネジメント検定(Ⅱ種) 取得
∟ポジティブ心理実践インストラクター資格 取得
✅当ブログのミッションは「苦労するワーママをひとりでも減らしたい!」です
4月スケジュールについてよくある質問┃「給食は?」「下校時間は?」など

入学前後、いちばん不安に感じやすいのが「毎日どんなスケジュールになるのか?」ということではないでしょうか。
特に4月は、学校も子どもも“慣らし期間”のため、予定が変則的になりやすい時期。
ここでは、よくある「給食はいつから?」「何時に帰ってくるの?」「学童はすぐ使えるの?」といった質問にお答えしていきます。
Q1:保育園はいつまで?学童はいつから使えるの?
保育園は基本的に3月31日までで終了となります。
学童は自治体や施設によりますが、4月1日から受け入れを開始しているところが多いです。

私が住んでいる世田谷区もそうでした。
ただし、入学式前や給食が始まるまでは「お弁当持参」などのイレギュラー対応で負担が増えがちです。
Q2:入学式ってどんな感じ?保護者は参加するの?
多くの学校では、入学式に保護者が2名まで参加可能です。
服装はセミフォーマルが主流で、所要時間は1時間半〜2時間程度。
式のあとは短時間で解散し、12時前には帰宅となる場合が多いです。

カメラマンがいて家族写真を撮影してくれる学校も多いようです。のちにそれを購入できるみたいです。我が家はそんなこと知らずに猛ダッシュで帰宅し家族で遊園地にいってきましたw
Q3:給食はいつから始まる?
給食の開始は学校によって異なりますが、入学式から約1〜2週間後が一般的です。
それまでは午前中に下校となるため、春休み明け〜給食開始まではお昼ごはんや学童に預ける場合でもお弁当の準備が必要です。

息子の学校も1週間後から給食開始でした。
我が家の場合は、春休み期間も含めると約2週間お弁当作りをする必要がありました。
最初の慣れない時期に、毎日お弁当を用意するのはちょっと嫌ですよねw
そんな我が家を助けてくれたのが、宅配食サービスです。
調理済みの冷蔵おかずをチンするだけで、すぐにお弁当や昼食の1品にでき、さらに夕食も作る必要がなくなるので本当に便利でした!
買い物も調理も不要になるので、4月の負担がグッと減らしたい方は是非以下の記事を参考にしてくださいね。
Q4:新一年生の下校時間は?
給食が始まるまでは午前下校(10:30〜11:30ごろ)が続きます。
給食開始後、ようやく午後までの授業になりますが、それでも4月中は早帰りの日が多くなります。
また、通常授業が始まっても、1年生のうちは14:00〜14:30ごろの下校が一般的です。
Q5:通常授業のスケジュールは?
学校によって異なりますが、1年生は4時間授業または5時間授業が基本です。
月・火・木・金は5時間、水曜日だけ4時間というパターンも。
また、時間割を5月上旬~中旬に配られますが、1年生のうちはこの時間割も変動します。
連絡帳に「自分の子供が書いてくる時間割」が正となるので注意しましょう。

我が家はそのことに6月中旬に気づきましたw
また、子どもの字が読めなくて理解できない日もあるので、クラスのママと連絡先を交換しておくとよいですよ!
Q6:登下校はいつまで親が付き添うの?
最初の1週間ほどは、登校時に途中まで付き添う家庭が多い印象でした。
ただし、学校や地域によっては「集団登校」や「登校班」がある場合もあるようです。
下校は基本的に子どもだけで帰ることになりますが、心配な場合は途中で待ち合わせるなど柔軟な対応が必要です。

我が家は、GW明けまで付き添いました。
我が家の場合は、一緒に登校しているときに、帽子を振り回して道路に飛ばしたり、猫を追いかけて走り出したりと、なかなか危なっかしい様子だったため、1か月以上付き添って様子を見ることになりました。
ただ、周りのお子さんを見ていると、その頃には9割以上(体感で97%くらい)の子どもが一人で登校していた印象です。
無理しすぎないことが大事|“やらない選択”でラクになる3つの心得

ここでは、小学校1年生の春を乗り越えたワンオペママから、小学校1年生の4月をラクに迎えるための3つの心得をお伝えしていきます。
- 完璧を目指さない
- 手放すための仕組化をする
- 周りや外部サービスを頼る
①完璧を目指さない┃持ち物もスケジュールも「完璧」を目指さなくていい
小学校生活が始まると、「忘れ物をさせてはいけない」「連絡帳をチェックしなきゃ」とつい気を張りがちですよね。
でも、最初から全部を完璧にこなす必要はないと感じています。
子どもが忘れ物をして叱られたり、自分で対処したりする経験も、大事な成長のひとつ。
親が先回りして全部やってしまうよりも、「見守る勇気」を持つほうが、子どもの自立につながります。
②手放すための仕組化をする┃朝の支度や帰宅後の流れも「仕組み化」で手放す
毎朝の準備や帰宅後のルーティンに追われる日々…。
そんなときこそ、親がやらなくても回る仕組みを作るのがポイントです。
たとえば、
こうした“ちょっとした仕掛け”があるだけで、子どもは驚くほど自分で動けるようになります。
③周りや外部サービスを頼る┃食事も「自分がやること」にこだわらないでOK
特に新学期は、親子ともに疲れが溜まりやすい時期。
そんなときに「毎日自分がやらなきゃ」と思い込むと、ママの心と体が持ちません。
ぜひ、職場の仲間や、家族、ママ友など頼れるものに頼りましょう!
我が家のように親族のサポートがなくママ友も…というような場合も、外部サービスがあるので安心です!
我が家では、夕飯用に頼んだ宅配食サービスのおかずをそのまま翌日の弁当に使うことで小1の壁を乗り越えました。
栄養士監修の宅配食サービスを活用することで、栄養バランスもバッチリ。
一般家庭では、到底実現できないようなバラエティ豊かな食卓と栄養バランスの両立が実現できます。
我が家はむしろ、以前よりも品目数が増え、健康的な食生活になったというメリットも!
「作らなきゃ」を手放すことで、ママにも子どもにも余裕が生まれますよ。
実際にやっておいてよかった「準備3選」

続いて、実際にわが家がやっておいて本当に助かった!と感じた“ラクになるための準備”を3つご紹介します。
「ちゃんとしなきゃ」より、「ラクに回す仕組みづくり」がポイントです。
1. 宅配食サービスをフル活用する
繰り返しになりますが、宅配食サービスは本当におすすめです。
春休み明け〜給食開始までは、毎日のお昼ごはんや学童用のお弁当づくりに追われがち。
まだ学校生活に慣れていない子どものフォローもしながら食事の準備…となると、ママの負担は限界に近づきます。
そんなときに頼りになったのが宅配食サービスでした。
調理済みの冷蔵おかずをストックしておくだけで、「とりあえずこれをチンすれば大丈夫!」という安心感が生まれます。
夕飯にも使えるし、翌日のお弁当にも詰められるので、時短&栄養バランスが叶う最強の味方です。
とはいえ、宅配食サービスは種類が多くて迷ってしまいますよね。
私が調べた限りでも、冷蔵・冷凍あわせて40以上のサービスがありました。
その中から、特におすすめの3社を厳選してまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。
2. 子ども自身でできることは仕組み化、ルール化しておく
新生活が始まると、朝の準備や帰宅後の流れでバタバタしがち。
でも、毎日親が「○○持った?」「宿題した?」と声かけし続けるのは、かなりのストレスになります。
そこで我が家では、“仕組み化”“ルール化”で親が抜けても回るように工夫しました。
こうしておくことで、親がいなくても「自分で流れをつかむ力」が自然と育っていきます。
3. 便利グッズを事前に購入しておく
時間と気持ちに余裕をつくるには、便利グッズの力を借りるのも立派な戦略です。
たとえば、
- 名前つけ作業を一瞬で終わらせられる名前シール
- 登下校の見守りに役立つ子ども用GPS(位置情報端末)
これらがあるだけで、日々の準備や不安がぐっと軽減されます。
特にGPSは、「何時くらいに帰ってきそうか」「今どこにいるか」がすぐに分かるので、親の安心感がまったく違います。
「ちゃんとしなきゃ」と思いがちな4月こそ、頼れるもの・仕組み・サービスに頼ることが、親子の笑顔を守るポイントです。
まとめ|完璧より「余白」! 4月は“手放す”ことから始めよう
新小学1年生の4月は、親にとっても子どもにとっても“慣れる”ことがいちばん大切な時期です。
でも、「予定を把握しなきゃ」「忘れ物をさせちゃいけない」と、つい頑張りすぎてしまうもの。
そんなときこそ意識したいのが、「手放すこと」です。
頑張るだけが正解じゃない新小学校1年生の4月。
「やらない選択」で、親子にとってゆとりあるスタートを切りましょう。
以上、こんママでした!

当ブログでは、
①ワーママが楽しく得やメリットをえるための「ワーママ術」
②「子どもの学び」にも楽しさを取り入れる重要性
について発信しています。
という方には、こちらの記事もおすすめです!
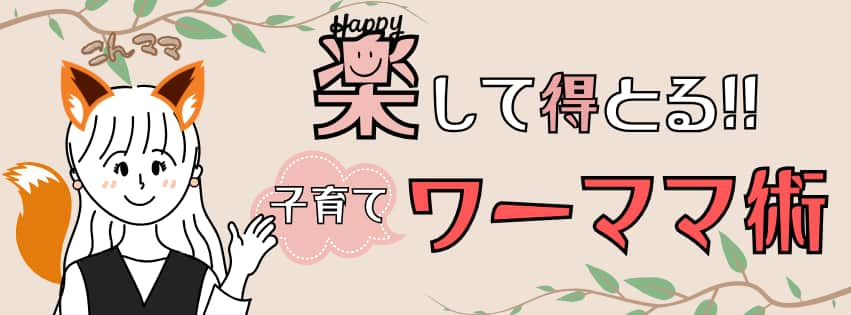







コメント