ワーママって、なんでこんなに毎日がしんどいんだろう?
そう感じて「ワーママ 辛い」と検索したあなたは、今まさに限界が近いのかもしれません。
仕事も育児も家事も、全部完璧にこなそうとするのは本当に大変なことです。
でも、実は“全部やらなくてもいい”って気づいていますか?
私自身、手放すことを覚えてから、日々のストレスがぐっと軽くなりました。
やらなきゃ、頑張らなきゃ、迷惑かけちゃいけない――そんな思い込みが自分を追い込んでいたんです。
この記事では、「今すぐ手放していいこと」を5つご紹介します。
読むだけで、少し心がラクになり、「辛い」から一歩抜け出すヒントが見つかるはずです。

✅7歳&4歳の2児の母
✅フルタイム30代管理職×夫単身赴任で不在
✅“頑張りすぎないワーママの暮らし”をサポートする情報を発信中。
∟フルタイムママ歴6年・単身ワンオペ歴2年
∟メンタルヘルス・マネジメント検定(Ⅱ種) 取得
∟ポジティブ心理実践インストラクター資格 取得
✅当ブログのミッションは「苦労するワーママをひとりでも減らしたい!」です
なぜワーママは「辛い」と感じるのか

毎日、全力で頑張っているのに、どうしてこんなに苦しいの?
ワーママが「もう無理…」と感じてしまうのには、明確な理由があります。
朝は子どもを保育園に送ってから職場へ直行し、仕事が終われば急いでお迎え。
帰宅後は夕飯の準備に掃除、入浴、寝かしつけ――息をつく暇もありません。
平日はもちろん、休日でさえ「家族のための時間」で埋まりがちで、リフレッシュできる余裕がないのが現実です。
そんな時間に追われる日々が、“孤独”を加速させてしまう要因にもなっています。
しかし、「私が頑張らなきゃ」と踏ん張っていても、限界はすぐそこにやってきます。
さらに追い打ちをかけるのが、「ちゃんとしなきゃ」という見えないプレッシャーです。
手作りのごはん、片付いた部屋、完璧な育児。どれも大切だけれど、全部を完璧にこなそうとするほど、自分を苦しめてしまうのです。

このように、「時間のなさ」「孤独」「完璧主義」の3つが複雑に絡み合って、ワーママは追い込まれていってしまいます。
今すぐ手放していい家事・思考5選
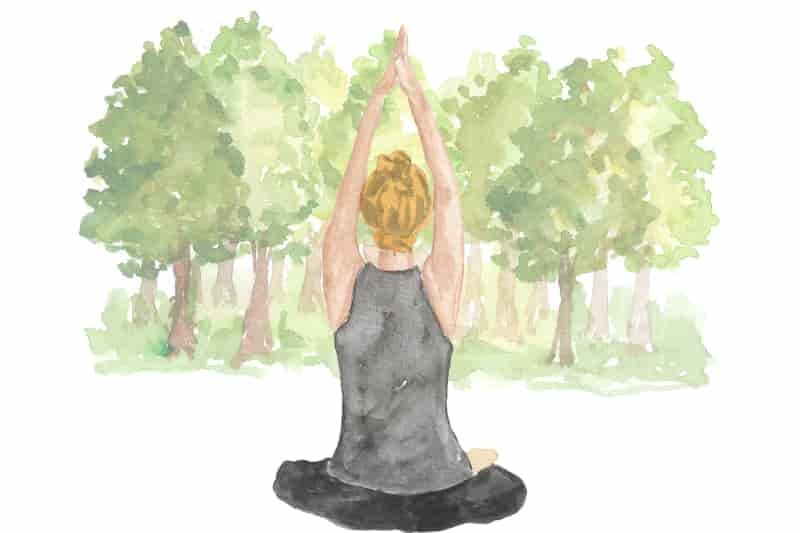
では、そんな苦しい状況から抜け出すには、どうすればいいのでしょうか?
答えは、「頑張ること」ではなく、「手放すこと」です。
すべてを完璧にこなそうとするのではなく、やらなくてもいいことを見極めて減らしていく。
それだけで、驚くほど心と時間に余裕が生まれます。
ここからは、実際に私が「手放してラクになったこと」を5つご紹介します。
献立づくりと毎日の料理
「夕飯どうしよう…」と考える時間が、実は地味にストレスだったりしませんか?
わが家では宅配食サービスを取り入れることで、夕飯づくりの負担が激減しました。
プロ慣習のサービスをちゃんと選べば栄養バランスも安心で、準備は温めるだけ。
子どもにも親にもやさしい選択肢です。
とはいえ、「どの宅配食を選べばいいの?」「子どもも食べてくれるかな…」と迷ってしまいますよね。
そんな方のために、子育てママに本気でおすすめできる宅食サービス3社を厳選しました。
以下の記事では、私が実際に使ってみて「これは良いサービス」と感じたものだけを紹介していますので是非参考にしてください。
「掃除=毎日やらなきゃ」という思い
部屋が散らかっているとイライラする、でも毎日掃除する時間も体力もない。
そんなときはロボット掃除機や家事代行サービスに頼ってOK。
「自分がやらなきゃ」という思い込みを手放すだけで、時間にも心にも余裕が生まれます。
とはいえ、実際には「いつどうやって掃除する時間を取ればいいの?」と悩む方も多いはず。
そんな疑問に答えるために、フルタイムワーママが実践している“掃除をラクにする工夫”をまとめた記事も用意しています。
忙しい毎日でも部屋が整う、リアルな方法をぜひチェックしてみてください。
家庭も仕事も完璧を目指す考え方
「家庭でも職場でも評価されたい」――その思いが自分の首を絞めていることも。
育児中は、ペースダウンして当たり前。
完璧を求めるより、「今日はこれだけできた」と自分を認める思考に切り替えてみましょう。
完璧にすべてをこなすのではなく、自分以外に任せられるタスクは、他にふるという選択も、とても大切です。
周りとくらべてしまう思考
SNSで見る“完璧なママ”や、職場でバリバリ働く同僚とつい自分を比べてしまうこと、ありませんか?
でも、その人たちの背景やサポート環境は、あなたとはまったく違うかもしれません。
比べるべきなのは他人ではなく、「昨日の自分」です。
少しでもラクになれた自分、笑顔で過ごせた時間――
それがあれば、もう十分花まるラインです。
「迷惑をかけてはいけない」という無意識の思い込み
そんな風に感じてしまっていませんか?
でも、周りに迷惑をかけない生き方なんて不可能です。
お互いさまで支え合うのがチーム、社会です。
“迷惑をかけたら終わり”じゃなく、“フォローし合う前提”で考えればいいんです。
今は育児で大変な時期、頼れるものは頼りましょう!
こうして見てみると、「やらなくてもいいこと」「手放していいこと」は意外と多いことに気づけると思います。
手放すことで、ようやく自分の笑顔が戻ってくる。
その一歩を、今から踏み出してみませんか?
「“やらなきゃ”の呪い」を早く手放すべき理由
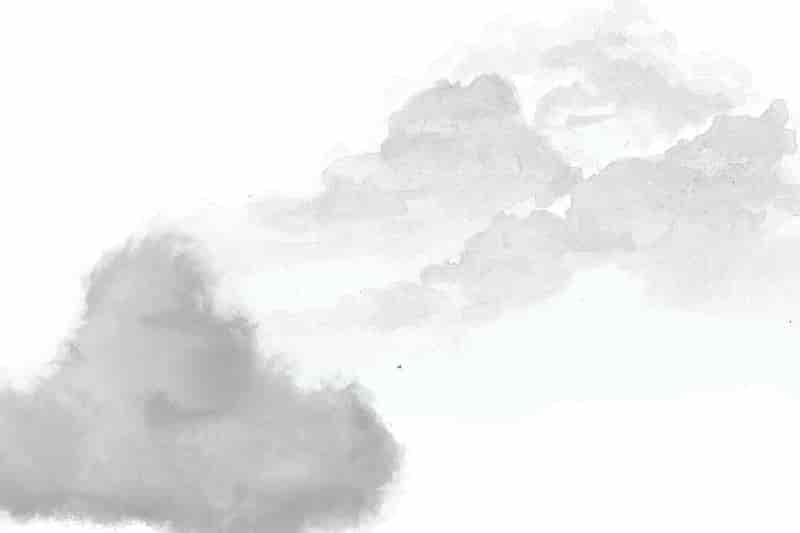
手放した方がいいことはわかっている。
でも実際には、「どうしてもやめられない」「やらなきゃって思ってしまう」。
そんなあなたを苦しめているのが、“やらなきゃの呪い”です。
それ、実は「思考グセ」です
「私がやらなきゃ」
「ここで休んだら迷惑をかける」
「母親なんだから当たり前」
そう思い込んでいませんか?
でもそれ、実は“現実”ではなく、あなたの中に染みついた思考グセです。
気づかないうちに、自分自身が厳しすぎるルールを課していしまっているのです。
「やめていい」と思えないのはなぜ?
頑張るのが当たり前になっている人ほど、「やめること=サボり」だと感じてしまうもの。
育児中なのに休んでると、罪悪感すら覚える。
でもそれは、あなたがダメなわけじゃなく、頑張り続ける環境に慣れすぎてしまっただけなんです。
仕事も家事も育児も「ちゃんとしなきゃ」と思うほど、自分がすり減っていく“思考の病”。
でも、もう大丈夫。
気づいた人から抜け出せるんです!!
このまま続けると、心も身体も壊れてしまう
実際に「やらなきゃ」を積み重ねた結果、体調不良や心の不調を抱えるママは少なくありません。
慢性的な疲労、イライラ、自己否定…。
それは、あなたが弱いからではなく、ずっと無理をしてきた証拠です。
だからこそ、「ちょっと手を抜く」「やらない選択をする」ことは、自分を守るために必要な行動なんです。
実際に少しずつ“手放す”ことでどうなった? ラクになった体験談

「手放すこと」の大切さに気づいてから、少しずつ行動を変えていきました。
すると、想像以上に心が軽くなり、生活が穏やかに変わっていったんです。
1人で背負わない選択が心を軽くした
まずやめたのは、「全部自分でやろう」とすること。
宅配食を取り入れて料理を減らし、掃除も家事代行を利用。
最初は「甘えなのでは?」と不安もありましたが、頼ってみたら、世界が変わったんです。
時間に追われてイライラすることが減り、呼吸が深くなったような気がしました。
そもそも、世の中というのは困っていることがあり(需要)、それを助ける人たちがサービスを提供し(供給)、生活の糧としている――そうやって社会は回っています。
誰かに任せることは、サボることではありません。
社会の仕組みに乗る、ごく自然な選択なんです。
家族全体に笑顔が増えた
ママに余裕ができると、家の空気がふわっとやわらかくなるものです。
「ママ、今日たのしいね」「うん、すごく楽しいね」そんな当たり前の会話が当たり前に日常に増えること。
改めて、余計なことは手放してよかったと心から思いました。
他人と比較せず、自分軸で暮らせるように
他のママと比べて落ち込んだり、SNSでキラキラした育児を見ては、もっと私も頑張らなくちゃと無理をしたり――
そんな、周りに左右されるなんてことも、ほぼなくなりました。
今は、「私たち家族にとってちょうどいい暮らし方」「自分にとって楽しい生き方」を大切にしています。
完璧じゃなくていい。
自分らしく笑えていれば、それで十分です。
まとめ|“やらない選択”があなたの毎日を変える
すべてを頑張らなくていい
ワーママだからって、いつも笑顔で、家もきれいで、仕事も完璧でいなきゃいけない――
そんなこと、本当はどこにも書かれていません。
むしろ、すべてを頑張りすぎるほど、心も身体もすり減ってしまう。
「やらなきゃ」を手放しても、あなたの価値は何も変わりません。
まずは小さな「手放し」から始めよう
最初から全部を変える必要はありません。
毎日の献立、掃除、仕事の優先順位…小さなことから手放してみるだけで十分です。
たとえば、今週の夕飯は宅配食にしてみる。
週末の掃除はロボットに任せる。
「今日も生きてた、えらい」と自分をほめる。
それだけで、少しずつ心が軽くなっていきます。
「辛い」から抜け出す最初の一歩は、自分を大切にすること
子どもや家族のために頑張るあなたこそ、まずは自分を大事にしてほしい。
「今日くらい、ラクしていいよ」
そう思えた瞬間から、毎日は確実に変わっていきます。
完璧なママじゃなくていい。
笑っているあなたがいるだけで、家族は十分しあわせです。
この記事が、「やらなきゃ」を少しでも手放すきっかけになれば嬉しいです。
無理せず、あなたのペースで――“頑張らない選択”を、今日から始めてみませんか?
以上、こんママでした!

当ブログでは、
①ワーママが楽しく得やメリットをえるための「ワーママ術」
②「子どもの学び」にも楽しさを取り入れる重要性
について発信しています。
という方には、こちらの記事もおすすめです!
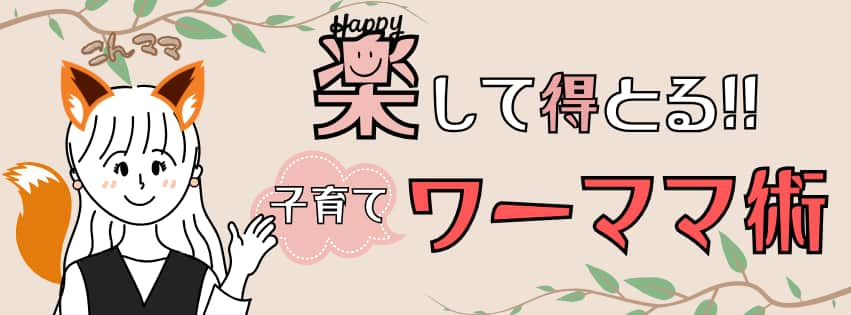






コメント